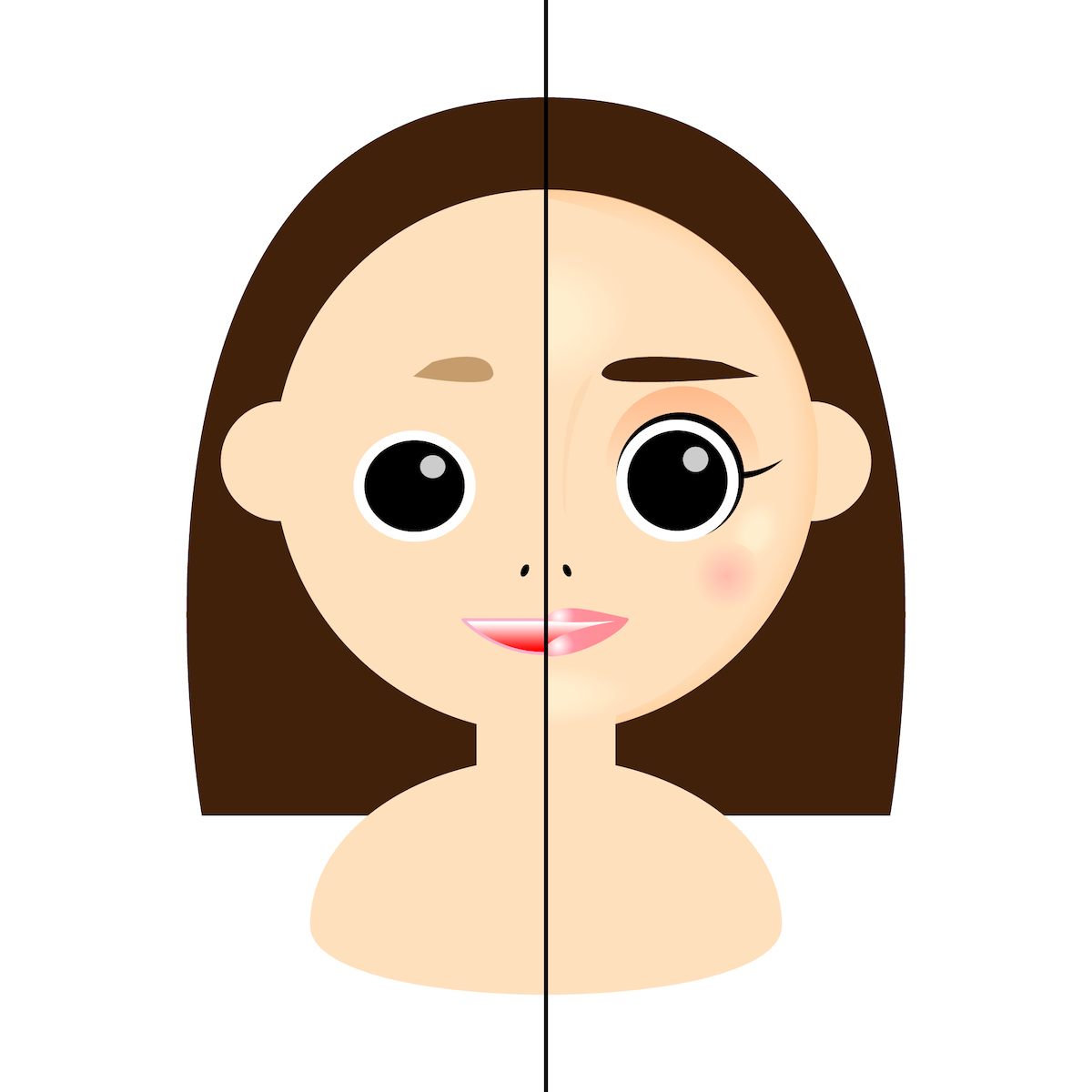新型コロナウイルス感染拡大のために様々方面で困難な状況が生じ、そのための募金が実施されています。
新型コロナウイルスによる募金が広く呼びかけられているのが、医療関係です。
集められたお金は、医療機関へのマスクや手袋、防護服など感染症の患者を治療するために必須のものを支援することに使われ、これらには人工呼吸器やベッドなどの医療機器の支援費用が含まれます。
特に感染拡大が急速に拡大している地域などに手厚く医療物資を届けることが行われています。
感染症の対応に携わる人件費にも支援金が使われている
さらには、感染症の治療に必要な医療機器を製造している事業者への支援とともに、感染症予防や治療のための研究や開発など医療体制の維持のために役立てられます。
加えて、医療機関だけでなく保健所や介護施設、障害者施設や保育所、学校や学童保育など直接・間接問わず、感染症の対応に携わる人件費にも支援金が使われています。
さらに、新型コロナウイルスで募金が集められる別の分野は、生活弱者に対するものです。
生活弱者は危機的な状況になると社会から孤立したりセーフティーネットから外れてしまう場合があり、支援の抜けや漏れがないように寄付されたお金が使われます。
生活弱者には、高齢者や低所得者、生活困窮世帯の子供やホームレスの人たちなどが含まれますが、そのような人たちに感染予防に効果的とされるマスクなどの提供したり、生活を助けるための食糧の配布などに役立てられたり、居場所を失った人たちを保護したりという活動に募ったお金が用いられます。
これらのお金は困窮している個人の方だけでなく、必要な物資を提供している支援団体のほかに、感染症への正しい知識が得られるよう啓もう活動を実施している団体などにも配布されています。
授業料が払えない大学生に対しての給付金を募ることが大学で行われている
加えて、在日外国人など公的なセーフティーネットの存在すら知らない人々に、多言語で必要な情報を発信することにも集められた基金が用いられます。
さらに、生活弱者とまでは言わなくとも、感染症が拡大により学業をあきらめざるを得ない学生を支援するために寄付を募っています。
具体的には授業料が払えない大学生に対しての給付金を募ることが大学で行われています。
また、もともと病気や事故などで親を亡くした子供の支援を行っている財団では、生活が困窮した遺児やその家族を支えるためにすでに奨学金を支払っており、街頭での募金ができないため、ホームページから支援してくれるよう呼びかけをしているようです。
さらに大きな打撃を受けているのが、文化・芸術・イベント等です。
寄付金控除での優遇を考えている人は確認が必要
さらにこの方法での寄付は法律の制定などにより、日本ユニセフのように寄付金控除を受けられ、税金面での優遇が得られるので、手軽にできる寄付の方法になりつつあります。
ただし、対象となるイベントには条件があるため、寄付金控除での優遇を考えている人は確認が必要となります。
ここまでは主に国内の状況について取り上げましたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴う募金は、世界の感染被害者に向けた支援にも用いられています。
グローバル化している今の世界では、この感染症が自分の国で収束しても、他の国で拡大しているなら、経済にしても通常の生活にしても、一向に正常化されることはありません。
そのため、特に金銭的な支援が必要な発展途上国などでは、感染拡大や感染予防の観点から潤沢な支援を得ることが必要です。
特に海外への支援金は、まずは医療機関にどんな支援が必要かを聞き取ることから始め、医療機関へマスクや防護服などの物資を購入して送付します。
海外への必要物資の提供となると、運搬費もかかることになります。
さらに衛生面での支援が必要な場所では、せっけんなど自らが感染予防ができる物資を配布することもします。
できる人ができる範囲で募金をすることで危機を乗り切る
特に今回の新型コロナウイルスへの対策として有効と考えられているのは、衛生面で気を付けることとともに、人と人との距離をとることにあるといわれていますが、字が読めないことや母国語が異なっていることで、感染予防についての正しい情報が伝わっていないことが想定される地域では、啓もう活動に集めた資金が使われることもあります。
また、難民キャンプなど人が密集している場所で感染を拡大させないために、感染者や感染の疑いがある人を隔離したり、速やかに医療機関で治療を受けられるようにするなど、的確な指示が出せるスタッフやそのスタッフを守るための防護服などの提供に資金が使われます。
国内外を問わず、この度の感染症で支援を必要とする人は大勢いるので、できる人ができる範囲で募金をすることで危機を乗り切っていきたいものです。