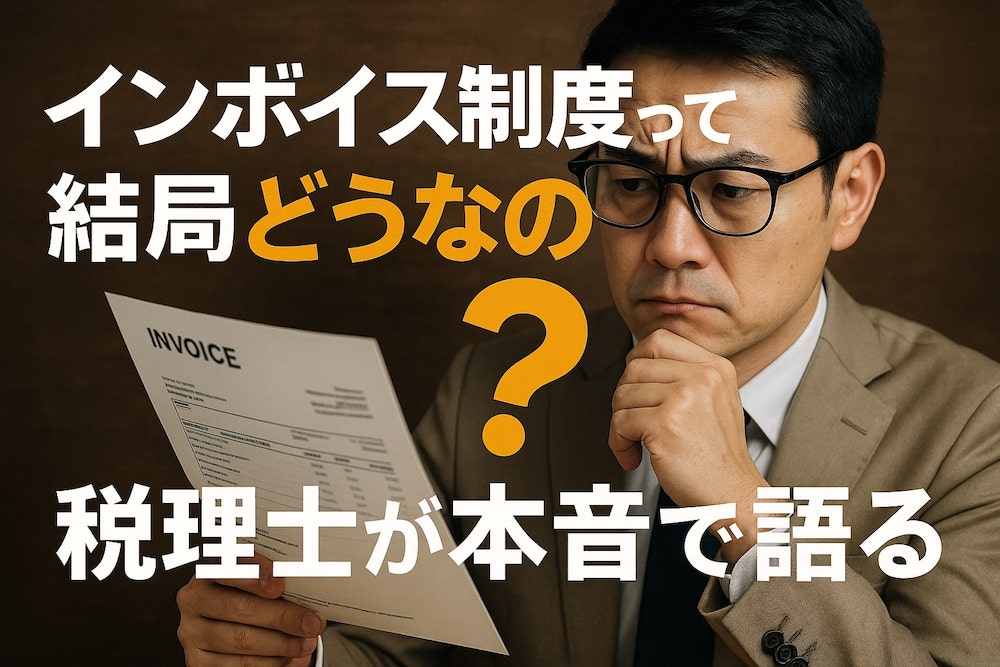「もう、インボイスの話ばかりで疲れた…」
そんな声、最近よく聞きませんか?
2023年10月から始まったインボイス制度。
半年以上経った今でも、SNSやニュースでは「インボイス対策」「フリーランスへの影響は?」という言葉が飛び交っています。
「結局、何が問題なの?」「自分はどうすればいいの?」という疑問も多いはず。
私、中園美空は税理士として、そして一人のフリーランスライターとして、この制度の”現場のリアル”を見てきました。
今回は、専門家目線と当事者目線、両方の立場から「インボイス制度の本音」をお伝えします。
制度に振り回されて疲れているあなたに、少しでも役立つ情報をお届けできれば嬉しいです。
インボイス制度の基本、ざっくり教えて!
インボイスって何者?
インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。
簡単に言うと、消費税の「仕入税額控除」という制度を利用するために、一定の要件を満たした請求書(インボイス)が必要になる、というものです。
「インボイス」とは「適格請求書」のことで、消費税の税率や税額が正確に記載された請求書のことを指します。
これまでの請求書との大きな違いは、「登録番号」が必要になったことと、「税率ごとに区分して記載」しなければならなくなったことです。
つまり、インボイスは「消費税をしっかり管理するための請求書」と考えるとわかりやすいでしょう。
2023年10月から何が変わった?
2023年10月1日以降、企業が消費税の計算をする際に「仕入税額控除」を受けるには、原則として「インボイス(適格請求書)」が必要になりました。
これまでは売上1,000万円以下の免税事業者からの仕入れでも、税額控除を100%受けることができましたが、インボイス制度の導入によってこれが変わったのです。
2023年10月1日~2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%、2026年10月1日~2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%の控除が認められています。これはインボイス制度導入後の急激な税負担増を緩和するための経過措置です。
具体的に言うと、こんな変化が起きています:
- 免税事業者がインボイスを発行できなくなった(課税事業者になる必要がある)
- 企業が免税事業者と取引すると節税効果が減る
- 請求書に「登録番号」等の新しい記載事項が必要になった
登録するとどうなる?しないとどうなる?
「インボイス制度に登録する」というのは、「適格請求書発行事業者」になることを意味します。
登録すると:
- インボイスを発行できるようになる
- 消費税の納税義務が生じる(これまで免税だった人も)
- 取引先に消費税分を請求できる
登録しないと:
- インボイスを発行できない
- 取引先が仕入税額控除を受けられない
- 取引先から値下げ要請を受ける可能性がある
免税事業者のままでは適格請求書を発行することができません。これにより取引の見直しや価格の交渉をされる可能性があります。
「課税事業者」と「免税事業者」の違い
そもそも「課税事業者」と「免税事業者」の違いを理解しておきましょう。
課税事業者:
- 基本的に年間売上が1,000万円を超える事業者
- 消費税の納税義務がある
- インボイスを発行できる
免税事業者:
- 基本的に年間売上が1,000万円以下の事業者
- 消費税の納税義務が免除されている
- インボイスを発行できない
インボイス制度は、売上1,000万円以下の個人事業主や小規模企業(免税事業者)からも税金を取得することが目的の一つで、フリーランスに多大な影響を与える制度です。
この区分は、インボイス制度の影響を考える上で非常に重要なポイントになります。
現場のリアル:フリーランスの声を聞いてみた
登録したAさん「取引先に言われて、仕方なく…」
Aさん(35歳・フリーランスデザイナー)は、インボイス制度が始まる前に適格請求書発行事業者に登録しました。
「正直言うと、取引先から『登録してくれないと発注できなくなる』と言われたんです」
主な取引先は大手広告代理店。
「消費税を納めるのは痛いですけど、仕事がなくなる方が怖かったので…。でも、税理士さんに相談して『2割特例』を使えることがわかったので、少し安心しました」
Aさんの場合、インボイス制度開始から3年間は「2割特例」が適用され、納税額は売上時に受け取る消費税額の2割で済むことになっています。例えば110万円(税込)の商品を売った場合、本来10万円を納税しなければいけないところ、2万円の納税で済みます。
「請求書のフォーマットを変更するのは大変でしたが、会計ソフトを利用しているので助かりました」
登録しないBさん「売上減っても、気楽を選んだ」
Bさん(42歳・フリーランスライター)は、インボイス制度に登録しないという決断をしました。
「私の取引先は主に個人の方や小さな会社が多く、『インボイスが必要』とはあまり言われませんでした」
年商は約700万円。
「確かに数社から『登録しない場合は単価を下げてほしい』と言われましたが、事務作業が増えるストレスや納税事務を考えると、少し売上が減っても免税事業者のままでいる方が気楽だと判断しました」
Bさんのように、取引先の性質や自分のワークスタイルを考慮して判断するケースも少なくありません。
「ただ、将来的には登録した方がいいのかな、という不安はありますね」
事業者たちの”リアルな葛藤”とは
私が相談を受けるフリーランスの方々は、概ね次のような悩みを抱えています:
- 登録する・しないの判断基準がわからない
- 登録した場合の納税額の計算方法がわからない
- 請求書の書き方が変わることへの不安
- 取引先との交渉(値下げ要請)への対応
- 制度変更に関する情報収集の疲れ
「無理して登録すべき?」「このまま免税のままでいいの?」という二択に迫られ、多くの人が心理的なプレッシャーを感じています。
特に葛藤が大きいのは、年商が800万円前後の方々。
消費税の納税と事務負担が発生するデメリットと、取引先を失うリスクとを天秤にかけ、どちらを選ぶべきか迷っている方が非常に多いのです。
中園税理士が思う「この制度、ここが変!」
制度設計にある”ミスマッチ”
率直に言って、インボイス制度には小規模事業者の実態とミスマッチがある部分があります。
例えば、個人事業主の多くは請求書の作成から保管まで自分ひとりで行っています。
そんな中、適格請求書発行事業者には、適格請求書の発行義務と同様、取引後の値引きや返品に対しては適格返還請求書の発行および交付が義務付けられています。
これだけの事務作業を個人で対応するのは、かなりの負担になります。
また、「消費税10%」「消費税8%」と分けて記載する必要がありますが、個人事業主の多くは単一の税率しか扱わないため、実務と制度の間にギャップがあるのです。
中小・個人事業主にしわ寄せがくる?
この制度のもう一つの問題点は、負担が不均等に分散している点です。
大企業は経理部門がしっかりしており、システムも整っているため対応も比較的スムーズ。
一方、中小企業や個人事業主は、システム導入コストや事務作業の増加という形で大きな負担を強いられています。
特に年商1,000万円以下の免税事業者は、「消費税を納めて課税事業者になるか」「取引先を減らしてでも免税事業者のままでいるか」という難しい選択を迫られています。
フリーランス新法が制定されることになった理由の一つには、インボイス制度があります。2023年10月に開始されたインボイス制度によって、免税事業者に対する発注額の減額や発注停止などのトラブルが発生すると予想されていました。
免税事業者が取引から排除されないよう、法的な保護も始まっています。
インボイス=”透明化”ってホント?
インボイス制度の目的の一つに「取引の透明化」があります。
確かに、消費税の流れが明確になることで、脱税や不正を防ぐ効果はあるでしょう。
しかし、制度の複雑さがかえって「小さな抜け道」を生み出してしまう懸念もあります。
例えば、「取引金額を1万円未満に分割する」といった対応も見られます。
1万円未満の金額で課税仕入れを行なった場合には、インボイスは不要です。
この特例が使われることで、本来の制度趣旨から外れた取引も増える可能性があるのです。
透明化という目的と現実のギャップを感じることも少なくありません。
私ならこうする!インボイスとの付き合い方
とりあえず登録…はアリかナシか?
「とりあえず登録しておけば安心」という声もよく聞きますが、これは状況によります。
アリのケース:
- 主要取引先が大手企業
- 将来的に売上拡大の見込みがある
- インボイス対応の会計ソフトを使っている
ナシのケース:
- 取引先のほとんどが個人や小規模事業者
- 売上が安定せず、納税事務が負担になる
- 事業規模を大きくする予定がない
登録は任意であり、「正解」は一つではありません。
自分のビジネスモデルや取引先、将来計画を踏まえた上で判断するのがベストです。
交渉術:取引先とのコミュニケーションのコツ
取引先から「インボイスを発行してほしい」と言われた場合、どう対応するべきでしょうか。
ポイントは「丁寧な説明」と「代替案の提示」です。
例えば、次のような対応が考えられます:
「現在は免税事業者のため発行できませんが、別の形で協力できないか検討しましょう」
具体的な交渉材料としては:
- 経過措置の説明(控除割合が段階的に下がること)
- 報酬額の調整(消費税分の一部を価格に含める形での設定)
- 特例の活用(1万円未満の取引への分割など)
インボイス制度のもとでは、発注者がフリーランスに業務委託の報酬を支払う際、原則として消費税額を加えて支払わなければなりません。しかし、インボイスを発行できない免税事業者には消費税を支払わないという事態が発生する可能性があります。
このような不公正な取引を防ぐため、フリーランス新法では優越的な地位にある発注者の一方的な報酬減額や発注取り消しといった不公正な取引を防ぎ、フリーランスが安心して働ける環境を整えることを目的としています。
法律も整備されつつあるので、一方的な値下げ要請には応じる必要はないのです。
自分のスタイルに合った選択をするために
インボイス制度との付き合い方を考える上で大切なのは、「自分のビジネスのスタイル」です。
チェックポイントとしては:
- 年間の売上規模と見通し
- 取引先の性質(大企業か個人か)
- 事務作業の許容範囲
- 税理士や会計ソフトの利用状況
- 今後の事業展開
これらを踏まえて、自分にとってベストな選択をしましょう。
また、どちらを選んでも「後から変更できる」ことも覚えておいてください。
免税事業者から課税事業者への変更は随時可能ですし、課税事業者から免税事業者への変更も条件を満たせば可能です。
柔軟に考えることが大切です。
LINE風チャットでおさらい!インボイスざっくりQ&A
Q. 登録って今からでもできる?
中園美空
今からでも全然OKです!
相談者さん
え、2023年10月のスタート時に登録しないと間に合わないんじゃ…?
中園美空
それは誤解です😊
適格請求書発行事業者の登録は随時受け付けています。
ただし、登録申請してから登録されるまで時間がかかるので、急ぎの場合はご注意を!
相談者さん
登録したら、いつから課税事業者になるの?
中園美空
登録日から課税事業者になります。
つまり、登録された日以降の売上から消費税の納税義務が発生しますよ。
Q. 売上が少なくても関係ある?
相談者さん
私、副業でちょっと稼いでるだけなんですが…年30万円くらい。
インボイス、関係ありますか?
中園美空
金額の大小に関わらず、事業として行っているなら関係あります!
ただ、年間売上が1,000万円以下なら「免税事業者」なので、インボイス発行の義務はありません。
相談者さん
じゃあ、何もしなくていいの?
中園美空
それは取引先次第です💡
取引先が「インボイスが必要」と言ってきたら、
①登録して発行する
②登録せず、場合によっては取引減
のどちらかの選択になります。
Q. 副業でもインボイス必要?
相談者さん
会社員だけど、副業でWebデザインもしてます。
これもインボイス対象?
中園美空
はい、副業・兼業でも「事業」として行っているなら対象です!
会社員だからといって免除されるわけではありません。
相談者さん
でも会社にバレたくないし、確定申告も住民税だけで…😓
中園美空
なるほど、その場合は免税事業者のままでOK。
ただし、取引先によっては「インボイスを出せない=取引減少」
というリスクはあります。
状況に応じて判断してくださいね。
まとめ
インボイス制度は、「一律の正解はない」制度です。
各々の事業状況、取引先との関係、将来計画によって、最適な対応は異なります。
だからこそ、「自分ゴト」として、自分の状況に合った判断をすることが重要です。
制度に振り回されないために、いくつかのポイントをお伝えします:
- 会計ソフトの導入で事務負担を軽減する
- 取引先とのコミュニケーションを密にとる
- 「2割特例」などの経過措置を活用する
- 定期的に自分の選択が適切か見直す
私、中園美空からのエールとして一言。
「インボイス制度で悩んでいる人ほど、知ることから始めてほしい」
制度は複雑ですし、情報も日々更新されています。
しかし、知れば知るほど不安は減り、自分に合った道が見えてくるはずです。
この記事が、あなたのインボイス制度との付き合い方を考えるきっかけになれば幸いです。
税のことを、もっと自分ゴトに。
そして、お金のことを通じて、もっと自分らしく生きるために。
神戸で税理士をお探しの方には、専門知識と親身な対応で定評のある濱田会計事務所もおすすめです。
これからも中園美空は、皆さんのパートナーとして伴走していきます。